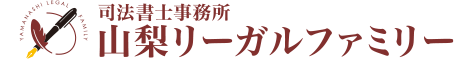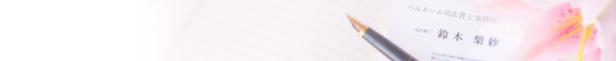遺産分割協議とは?
亡くなった方が遺言書を残していなかった場合や、遺言書があっても、そこに記載のない財産があった場合、相続人全員が話し合いによって誰が何を相続するかを決定していくことになります。
この話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。
遺言書があれば、その内容が優先され、遺言書に記載されている通りに財産を分けます。
一方で、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。相続人全員の合意が得られれば、法律上の相続分とは異なる遺産分割をすることも可能になります。
遺産分割はお早めに!
遺産分割をするのは、相続人の皆様にとって気が重い場合もあるでしょう。しかし、相続登記が義務化となった以上、遺産分割協議をしないまま放置しておくわけにはいきません。
遺産分割協議でどのような場合に注意が必要なのか以下、ポイントを挙げていきます。
遺産分割協議チェックリスト
✔︎相続人のなかに未成年者がいないか
相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければなりません。
例えば夫が死亡して、その妻と未成年の子が相続人となる場合は、妻と特別代理人が子に代わって遺産分割協議に参加することになります。
母親と子は、遺産分割協議においては利害が対立するため、母親は未成年の子の代理人になることはできないのです。
✔︎相続人のなかに認知症の方がいないか
相続人のなかに認知症の方がいる場合には、家庭裁判所によって成年後見人を選任しなければ遺産分割をすることができません。
そして何よりも注意が必要なのは、成年後見人がつく場合には、その方の法律上の相続分を渡す必要があるということです。
相続財産のほとんどが不動産である場合などは、不動産を分割してあげるというわけにはいきませんから、なかなか大変です。
遺産分割協議では人間関係の揉め事だけではなく相続人の高齢化などによって協議が難しくなることもあるため、やはり遺言書の作成は必須です。
✔︎住み続ける(または将来住む予定がある)相続人がいる
亡くなった方の不動産に、将来住む予定がある相続人がいる場合には、不動産の名義をその相続人の名義に変える必要があります。
例えば、亡くなった夫名義の不動産に妻がそのまま住み続ける場合。子供がいない夫婦の場合には、夫の親(親が亡くなっていれば兄弟に捺印をもらえないと家に住み続けられません…。悲惨です。
話し合いがまとまらなかったときは・・・
遺産分割協議を行っても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で「遺産分割調停」という手続きをします。
遺産分割調停とは、裁判所の調停委員という第三者が間に入り、話し合いにより解決するものです。
遺産分割調停でも話がまとまらないときは、「遺産分割審判」という手続きに移行します。
裁判官が相続財産について様々な調査をしたうえで、裁判により遺産分割を決めることになりますし、もし審判の結果に不満がある場合は、高等裁判所に不服申立てをすることもできます。